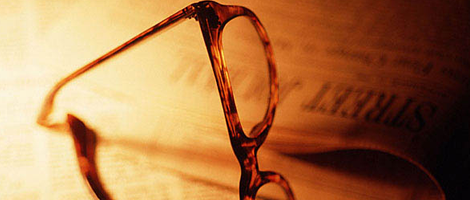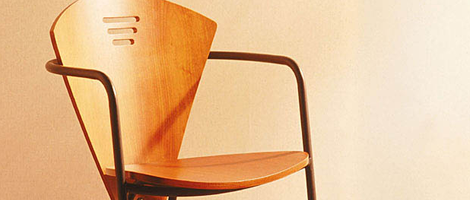このページをご覧の方は、突然の相続に直面し、「何から始めればよいか分からない」とお悩みかもしれません。 相続人の確認や遺産の分け方、戸籍の収集など、相続には多くの手続きと判断が必要です。
実際、当事務所にも「相続の全体像が分からない」「遺言書をどう書けばいいのか分からない」とご相談に来られる方が後を絶ちません。
まずは、どのような手続きが必要かをご説明します。
相続の第一歩:死亡届の提出と葬儀の手配
ご家族が亡くなられた場合、まずは死亡届を役所へ提出する必要があります。提出期限は「死亡を知った日から7日以内(国外の場合は3か月以内)」です。 実際は、葬儀社が代行して提出することが一般的ですので、まずは葬儀社に連絡し、今後の流れについて指示を仰ぎましょう。
葬儀が終わると、いよいよ相続に関する本格的な手続き(戸籍取得や遺産分割協議など)が始まります。
一人で抱え込まず、専門家にご相談ください
相続は一度きりの経験であり、すべてをご自身で行うのは大きな負担です。 当事務所では、相続や遺言に関するご相談を初回無料で承っており、専門家が丁寧に対応いたします。
分かりやすく、安心して任せられる相続サポートをお探しなら、ぜひ一度ご相談ください。
相続の基礎知識|種類・遺言書・相続人・相続割合について
相続は必ずしも「しなければならない」ものではありません。相続する権利はありますが、義務ではなく、マイナスの財産(借金など)も含まれることから、慎重な判断が大切です。
相続の方法は大きく分けて3つあります
まずは「単純承認」です。これはプラスの財産もマイナスの財産もすべて相続する方法で、相続開始後に特に何もしなければ自動的に単純承認したことになります。
次に「限定承認」があります。これは、相続によって得た財産の範囲で借金を返し、残った財産があれば相続する方法です。ただし、相続人全員の一致が必要で、手続きも複雑です。
最後に「相続放棄」があります。文字通り、一切の相続財産を放棄する方法で、借金の多い相続や、他の相続人に譲る目的でも選ばれます。相続を知ってから3か月以内に家庭裁判所で申述手続きが必要です。
遺言書の有無は早めに確認を
相続手続きを始める前に、遺言書の有無を確認しましょう。故人が生前に保管場所を伝えていればスムーズですが、そうでない場合は遺品の中から探す必要があります。 また、公証役場や専門家の事務所(行政書士・弁護士など)に保管されていることもあります。
遺言書があれば、その内容に従って相続が行われます。遺言書がなければ、相続人同士で話し合い(遺産分割協議)を行うことになります。
誰が相続人になるのか
法律で定められた相続人(法定相続人)は、被相続人の配偶者を中心に、以下の順で決まります。
第一順位は、配偶者と子ども。 第二順位は、配偶者と父母。 第三順位は、配偶者と兄弟姉妹です。
配偶者は常に相続人になります。再婚していてもその権利は失われず、逆に離婚した元配偶者には相続権はありません。胎児は生きて生まれれば相続人となりますし、養子も相続権を有します(特別養子でない限り、実父母の相続権も残ります)。
法定相続分(民法で定められた割合)
相続人同士の取り分(法定相続分)は、以下のように法律で定められています。
第一順位の場合、配偶者と子どもはそれぞれ1/2ずつ。 第二順位では、配偶者が2/3、父母で1/3を分け合います。 第三順位では、配偶者が3/4、兄弟姉妹で1/4を分け合います。
なお、共同相続人のうち一方がすでに亡くなっている場合、その分は他の相続人が引き継ぎます。
相続は一生に何度もない経験だからこそ、最初の一歩から安心できるサポートが必要です。 神戸で相続や遺言にお悩みなら、ぜひ行政書士 井原総合法務事務所にご相談ください。
遺産分割協議と遺産分割協議書の作成について
遺言書がない場合、法定相続人全員による話し合い(遺産分割協議)を行い、誰がどの財産をどのような割合で相続するかを決定します。 法定相続分にこだわる必要はなく、全員が納得すれば異なる割合で分けることも可能です。
遺産分割協議は、全員が揃って行うのが理想ですが、書面による持ち回りでも問題ありません。重要なのは、相続人全員の合意が必要であり、ひとりでも欠けた協議は無効となる可能性があるという点です。そのためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍を正確に集め、相続人を確定する必要があります。
遺産分割協議書の作成
協議が成立したら、遺産分割協議書を作成します。この書類はやり直しが原則できないため、内容にしっかり納得した上で作成することが大切です。
協議書は相続人の人数分を作成し、全員が署名・実印を押印したうえで1通ずつ保管します。また、印鑑証明書も添付します。 この協議書は、後日のトラブル防止のための重要な証拠資料になります。少しでも不安があれば、専門家に相談しましょう。
当事務所では、遺産分割協議書の作成をはじめ、相続全般の手続きを丁寧にサポートいたします。
遺産分割後の具体的な手続き
協議書をもとに、相続財産の名義変更などを行います。例えば、不動産は法務局で登記手続き、預貯金は銀行で口座名義の変更、また農地・事業・借地権の相続なども必要に応じて進めていきます。
相続手続きをされる多くの方が、途中で「手続きが煩雑で分からない」「仕事が忙しくて時間がない」とご相談にいらっしゃいます。 実際には、同時進行で仏壇・お墓・法要なども重なり、手続きだけに集中できないのが現実です。
だからこそ、相続・遺言に強い専門家に任せることで、ご負担を大幅に軽減できます。
相続・遺言サポートサポート事務所業務対応エリア
 兵庫県全域。神戸市中 央区、神戸市垂水区、神戸市須磨 区、神戸市東灘区、神戸市灘区、神戸市西区、神戸市兵庫区、神戸市長田区、神戸市北区、芦屋市、西宮市、尼崎市、伊丹市、明石市、加古川市、姫路市、たつの市、相生市、赤穂市、淡路市、洲本市など。
兵庫県全域。神戸市中 央区、神戸市垂水区、神戸市須磨 区、神戸市東灘区、神戸市灘区、神戸市西区、神戸市兵庫区、神戸市長田区、神戸市北区、芦屋市、西宮市、尼崎市、伊丹市、明石市、加古川市、姫路市、たつの市、相生市、赤穂市、淡路市、洲本市など。
※行政書士法により、行政書士には守秘義務が課せられております。正当な理由なく、お客様の秘密を漏らすことはございませんので、安心してご相談、 ご依頼ください。